| さて、どうなる?今年のしし座流星群 |
| 吉川 真(宇宙科学研究所) |
| 33年ぶりの「しし座流星群」も話題になってからすでに4年目、つまり今年のしし座流星群が4回目となります。4回目ですが、皆さんすでにご存じのように、日本では今年が最も期待されている年なのです。(3年ほど前に「あすてろいど」24号にしし座流星群について書きましたが、その後、思いもよらないいろいろな展開があり感慨深いです。) 最初の1998年では、今回のしし座流星群の最初の年として、マスコミなどでも大きく取り上げられ、多くの人が流星を見に出かけました。結果的には、雨のように流れる流星雨こそ見られませんでしたが、明るい流星もかなり流れ、それなりの数の流星が見られました。次の1999年は、日本は好条件ではなかったのですが、ヨーロッパでは降るような流星が見られました。実際、ヨーロッパ方面に行かれた大塚勝仁さんや矢野創さんが、降るような流星の観測に成功しています(「あすてろいど」30号にお二人の報告が掲載されています)。また、このときの流星群については、デイビッド・アッシャー氏らの事前の予想がぴたりと的中して、一躍注目の的となりました(「あすてろいど」29号参照)。 そして、このアッシャー氏の予想では、2001年には流星が本当に沢山流れる可能性が高く、それも日本で見られるというのです。ちなみに、2000年は予想でもあまり流れないということでしたが、実際にもそれほど出現はしなかったようです。ということで、今や流星界では話題の人(?)となったアッシャー氏ですが、現在は、日本では日本スペースガード協会の客員研究員として、イギリスではアーマー天文台の研究員として、イギリスと日本とを行き来しながら研究を続けています。ちょうどよい機会ですから、日本にいるときには各地で講演もしていただいており、何と今年だけでも10数回の講演をお願いしています。その講演の様子につきましては、「あすてろいど」の33号や35号で、加藤公子さんと守山義之男さんが紹介されています。 そのアッシャーの予想ですが、今年については次のようになっています。ここで、ZHRとは、Zenithal Hourly Rateと呼ばれるもので、流星観測に理想的な状況を仮定した上で輻射点が天頂にある場合に1時間あたりに流れる流星数のことです。実際に見える数はこの3分の1くらいになると思われます。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
この表を見ると、11月19日の未明に、2回、多数の流星が流れる可能性があり、それを日本から見ることができるというわけです。流れる個数として仮にZHRの3分の1としても、1時間あたりに数千個の流星が流れるわけですから、これはめったにないことです。本当に流れたら、きっと感動的な光景になるでしょう。ちなみに、アッシャー氏の理論によると、2:31の流星群は1699年にテンペル・タットル彗星から放出された塵であり、3:19の流星群は1866年の塵によるものということです。これらは、それぞれ9周回と4周回前に出された塵になるわけです。 ただ、注意すべきことは、アッシャー氏の理論では流星群が現れる時刻は非常に正確に予測できるのですが、流れる数の方はある程度推測に頼ることになっているということです。つまり、過去にテンペルタットル彗星から放出された塵がどのような軌道になっているかについては正確に計算できるのですが、その軌道上にどのくらいの数の塵があるかについては、理論からでは分からないわけです。流れる数については、地球が塵の流れのどの付近を横切るのかということに加えて、過去のしし座流星群のデータなども使って推定しているのだと思います。仮に、地球が塵の流れを横切るときに、たまたまそこにあまり塵がなかった、というようなことも否定はできないわけですね。逆に、地球が流れを横切るときに、そこに濃い塵の流れがあるかもしれないわけで、そうなれば、流星雨どころか流星嵐ですら出現するかもしれません。ということで、流れる数については相変わらず正確な予測はできないわけですが、是非、沢山流れることを期待したいですね。 |
|||||||||||||||||
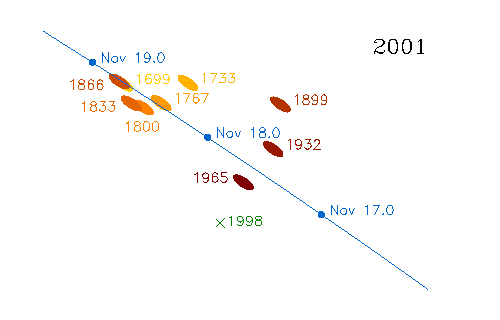 地球の軌道としし座流星群の流れの一。McNaught-Asherによる。斜めの線が地球の軌道であり、楕円形のそれぞれは、記載されている年号の年にテンペルタットル彗星から放出された塵の流れが黄道面(地球の軌道面)を横切る位置を示している。この図で、1699と1866と書かれた楕円形の部分に地球が入るときに沢山の流星が流れると考えられている。地球の軌道上に記載された時刻は世界時である。また、×印は、今回のテンペルタットル彗星の軌道と黄道面の交点を示す。 |
|||||||||||||||||
さて、このように今回のしし座流星群については期待が高まっていることもあって、様々な催しも企画されています。そのすべてについて紹介することは到底不可能ですから、ここでは、その中の2つだけご紹介したいと思います。 1つは、「高校生天体観測ネットワーク」というもので、これは、1998年のしし座流星群をきっかけとして始まったもので、全国の高校生が同じ方法で同時に天文現象を観測しようとするものです。今までは、しし座流星群を初めとして、月食や木星食の観測をしてきました。そして今年のしし座流星群でも全国的な観測を計画しています。ホームページは、http://www.astro-hs.net/にあります。 もう1つは、しし座流星群をインターネットで生中継しよう、という試みです。天文現象をインターネット中継しようという試みは、今までもたとえば日食などで行われてきました。日本スペースガード協会が主催しましたマダガスカル日食ツアーでも、参加者の和田英一さんが中継を試みられました。この中継の様子は、http://www.live-eclipse.org/でご覧になれます。これと同様なことを、しし座流星群でも行おうということで、ライブ!レオニズという計画が進行中です。そのホームページは、http://www.live-leonids.jp/です。このようなインターネットによる生中継はいくつかのグループが計画しているようで、まさにネットワーク社会での天体観望ですね。 このような企画以外にも、インターネット上では、しし座流星群に関する様々なページがあります。こちらもすべてを網羅することなど不可能ですが、例えば日本流星研究会(http://www.nms.gr.jp/)や国際流星機構(http://www.imo.net)からネットサーフィンを始められるとよいのではないでしょうか。肝心なページを忘れていました。アッシャー氏のホームページです。 http://star.arm.ac.uk/~dja/dja.html このようにインターネットはインターネットとして非常に便利で有益ですが、やはり天体観望は肉眼が基本です。是非、風邪などひかないような万全の準備をして、11月19日の未明には夜空を眺めてみてください。問題は、お天気ですね。こればかりは、どうにもなりません。また、この日は月曜日ですから、学校や仕事にも差し支えないようにしないといけないですね。もしかすると一生に一度だけのものになるかもしれませんから、是非、見逃さないようにしたいですね。それと、「流星群」は事前に騒ぎ立てると出ないというジンクスがあります。ということで、あまり騒がないで期待しましょう。 |
|||||||||||||||||